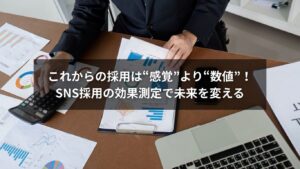「公務員がSNSで発信してるって本当?」「地方の行政がSNSで注目されるなんて信じられない」
あなたもそんなふうに思ったことはありませんか?正直、私も以前はそうでした。
ですが最近、「公務員」「地方」「SNS」という言葉がセットで語られる場面が増え、
行政機関の広報活動が大きく変わりつつあるのを感じています。
とくに地方自治体では、若年層への情報発信や住民との関係強化にSNSを使う動きが加速中。
「まさか公務員がTikTokで踊ってる!?」と驚く場面すらあり、
SNSを使った発信がどれほど影響力を持つか、見過ごせない時代になっています。
では、なぜ今「公務員×地方×SNS」がここまで注目されているのでしょうか?
この記事では、その理由と成功自治体に共通する“バズる仕掛け”を解説していきます。
Contents
公務員×SNS=信頼?地方の新しい情報発信手段とは
まず、公務員がSNSを使う目的について触れておきたいと思います。
単なる話題づくりではなく、SNSは「住民との接点」を築く重要なツール。
従来の広報紙や市報だけでは届かなかった若年層へ、
リアルタイムでわかりやすく伝えるには、やはりSNSが最適です。
例えば、災害時の緊急連絡、ワクチン接種の受付開始、イベント告知など、
情報の即時性が求められる場面では、SNSが真価を発揮します。
それだけでなく、「公務員」のリアルな仕事ぶりを発信することで、
行政機関に対する親しみや信頼感を得やすくなるという副次効果もあるのです。
地方自治体がSNSで“バズる”ために必要な視点
では、どんな「地方」の「公務員」アカウントがバズっているのでしょうか?
共通しているのは、以下のようなポイントです:
- 親しみやすさのある人柄(中の人のキャラ)
- タイムリーかつ生活に密着した情報発信
- 画像・動画の工夫(ショート動画・ライブ配信など)
- 地域の魅力を“ストーリー”で伝える工夫
特に注目すべきは、“自治体らしさ”を崩さずに個性を出している点。
「公務員だから堅い投稿しかできない」なんて思い込みはもう通用しません。
逆に、まじめな内容を“ゆるキャラ風”に伝える手法が、むしろバズる傾向にあります。
SNSを運用する公務員が注意すべきポイント
とはいえ、すべてが順風満帆というわけではありません。
「地方」の「公務員」が「SNS」を使ううえで、気をつけるべき落とし穴もいくつか存在します。
たとえば、
- 過度な情報開示(プライバシーの配慮不足)
- 誤解を生む表現(意図しない炎上)
- 運用体制の不備(担当が突然変わるなど)
こうしたリスクを防ぐには、あらかじめガイドラインを整備することが欠かせません。
また、自治体内にSNSを理解する職員を増やし、チームで運営することも大切です。
あなたの自治体でもSNS発信を始めるには?
もしあなたが地方自治体に関わる「公務員」なら、
「うちの町でもSNS、始めた方がいいのかも…」と感じているのではないでしょうか?
結論から言えば、SNS活用は遅かれ早かれ必要になるはずです。
まずは小さなところからスタートするのがコツ。
・毎月1本の情報発信
・Instagramでイベント写真を投稿
・TikTokでまちの観光地を紹介
そんな些細な試みでも、住民との距離は確実に縮まります。
SNSの良さは、始めるハードルが低い点にもあります。
あなたの自治体の魅力、もっと多くの人に届けてみませんか?
まとめ|公務員のSNS活用は“地方”の未来を変える
いま、「公務員」「地方」「SNS」というキーワードは、
単なる流行ではなく、新しい行政のあり方を映すキーワードになりつつあります。
あなたの一歩が、自治体の未来をつくるきっかけになるかもしれません。
「うちの役所には関係ない」と思わず、まずは試してみてください。
次のバズは、あなたの自治体かもしれませんよ。