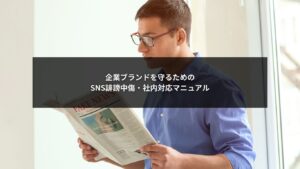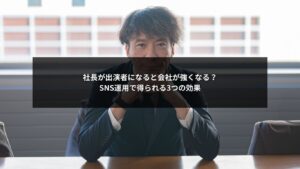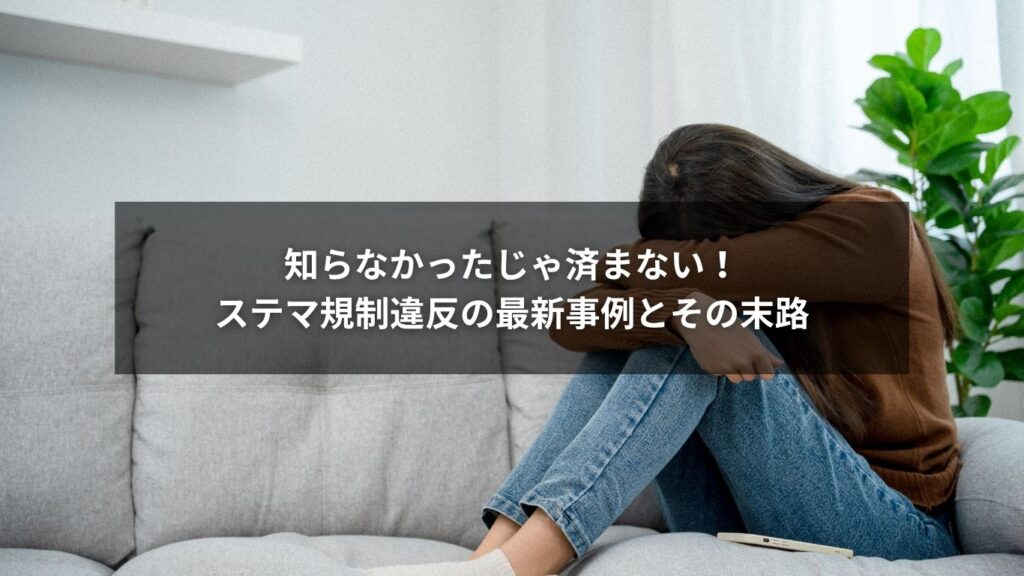
「うっかりのつもりが違反になるなんて」
そんな声をよく耳にします。正直、あなたもSNSやブログで
PR活動をするとき、「これは大丈夫だろう」と思って
軽く見てしまったこと、ありませんか?
でも、今の時代、ステマ規制違反は甘くありません。
2023年10月の景品表示法改正を機に、明確に「有償PR」か
どうかを表示しなければ、広告主もインフルエンサーも
違反者として扱われる可能性があるのです。
この記事では、実際に起きたステマ規制違反の事例を
紹介しつつ、なぜそれが問題になったのか、
そしてあなたが気をつけるべきポイントを
ネットマーケティングの専門家としてお伝えします。
Contents
ステマ規制違反とは?よくある誤解とその背景
まず押さえておきたいのが、ステマ規制違反の定義です。
正式には、「ステルスマーケティングのうち、広告であることを
隠して商品やサービスを宣伝する行為」を指します。
たとえば、「この商品マジでおすすめ!」と
インフルエンサーが投稿していたとして、
実は企業から報酬や商品提供を受けていた場合。
その事実を明示せずに宣伝していれば、
景品表示法違反=ステマ規制違反に該当します。
つまり「広告であることを明確に示していないPR」は、
どんなに善意でもNG。ここを見落としてしまう人が
本当に多いのです。
【事例①】人気YouTuberが企業案件を「私物」と偽って炎上
2024年に話題になったステマ規制違反の事例として、
某YouTuberが企業から提供された美容アイテムを
「自腹で買った」と紹介したケースがあります。
コメント欄には「信じて買ったのに」「裏切られた」
といった批判が殺到。結果、数万人の登録解除と
案件打ち切りが続出しました。
提供品であれば、「#PR」「提供:○○」などの明示が必要。
そこを怠ったことで、企業側も共に問題視されました。
【事例②】地域活性化プロジェクトが逆効果に?
行政主導のキャンペーンでもステマ規制違反の事例は
発生しています。ある地方自治体が、若者向けに
観光地をPRする目的でインフルエンサーを招いた際、
「旅行体験」として紹介させた投稿の一部に「広告」表記が
なかったことで消費者庁から注意を受けたのです。
実際には旅費・宿泊費が支払われており、れっきとしたPR案件。
「個人の体験談のように見える演出」が
ユーザーに誤解を与えたとして指摘されました。
ステマ規制違反にならないために、あなたがすべき3つの対策
それでは、ステマ規制違反を防ぐにはどうしたらいいのか?
ネットマーケティングの立場から、すぐ実践できる3つの対策を
お伝えします。
① 「PR」「提供」「広告」など明確な表記を!
何よりも大事なのは、「これは広告です」と
誰が見てもわかる表現を使うことです。
Instagramなら「#PR」、YouTubeなら概要欄冒頭に
「この動画には広告が含まれます」と記載。
ユーザーに誤認させないための透明性が求められています。
② クライアントと契約時に“表記ルール”を確認
あなたがインフルエンサーやライターなら、
案件を受けるときに「広告表示は必須ですか?」と
必ず確認しましょう。企業もルールを理解していない
場合があるため、逆にリードしてあげる意識が重要です。
逆に企業側も、発注時に表示ルールを明記し、
ステマ規制違反を回避する体制を整えるべきです。
③ “レビュー風”や“体験談風”の表現に注意
最近特に問題視されているのが「個人の感想のように
見せかけたPR」。これはステマ規制違反の温床になります。
「この商品に感動しました!」といった表現を使う際も、
提供品であれば明示を忘れずに。
文章に自然な形で「広告であること」を差し込みましょう。
まとめ:信頼を守るために、透明性は義務
ステマ規制違反は、「知らなかった」では通用しません。
今回ご紹介した事例のように、信頼を失うリスクは
あなたが想像する以上に大きいものです。
でも、逆に言えば、ルールを守って誠実に伝えることで
「この人のレビューなら信頼できる」と
ファンとの関係性を深めることもできます。
ネットマーケティングに関わるあなたこそ、
情報の透明性と誠実さを大切にしていってください。
その積み重ねが、長期的な信頼と成果につながります。
※この記事は2025年7月時点の法令をもとに執筆しています。
最新のステマ規制情報は消費者庁のサイトをご確認ください。